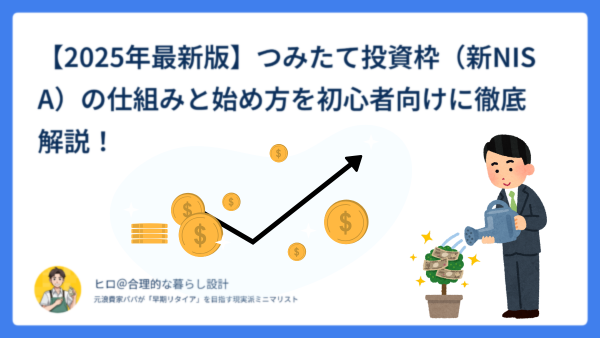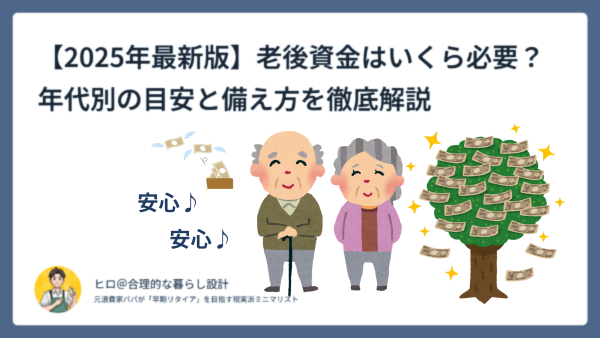【2025年最新版】iDeCo(イデコ)の仕組みと始め方を初心者向けに徹底解説!

1. 導入(要約)
iDeCo(個人型確定拠出年金)の仕組みを初心者にもわかりやすく解説します。
iDeCoは、自分で毎月積み立てたお金を運用し、老後資金をつくるための公的制度です。
掛金が全額所得控除になるなど、節税効果が大きいのが最大の特徴です。
2022年・2024年の制度改正により、加入可能年齢が65歳未満まで拡大、
さらに2025年以降も継続して非課税での受け取り方法(年金・一時金)が整備されています。
2. iDeCoとは
iDeCo(Individual-type Defined Contribution Plan)は、
「自分で積み立て」「自分で運用し」「自分で受け取る」年金制度です。
国民年金や厚生年金などの公的年金に“上乗せ”する制度であり、
働き方や職業に応じて掛金上限額が異なります。
加入は任意ですが、税制優遇が強力なため、
資産形成+節税を両立させたい人にとって非常に有効な選択肢です。
3. 節税の仕組み(3つの非課税メリット)
| 区分 | 内容 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 掛金拠出時 | 掛金が全額所得控除 | 所得税・住民税が軽減 |
| 運用期間中 | 運用益が非課税 | 通常20%課税がゼロ |
| 受取時 | 公的年金控除・退職所得控除 | 税負担を最小化できる |
例:会社員が毎月2万円を拠出
→ 年間24万円 × 所得税・住民税30%=約7.2万円の節税効果
(※実際の節税額は所得や扶養状況により異なります)
4. 加入資格と掛金の上限額
| 区分 | 加入可否 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 自営業者(第1号被保険者) | ○ | 68,000円 |
| 会社員(企業年金なし) | ○ | 23,000円 |
| 会社員(企業型DCあり) | ○(一部制限) | 20,000円 |
| 公務員 | ○ | 12,000円 |
| 専業主婦(第3号被保険者) | ○ | 23,000円 |
📍65歳未満まで加入可能
以前は60歳未満でしたが、改正で加入可能期間が延長されています(2022年施行)【出典:国民年金基金連合会】。
5. 始め方と運用の流れ
ステップ①:金融機関を選ぶ
銀行・証券・保険会社など、多くの金融機関がiDeCoを取り扱っています。
運用商品・手数料・サポート体制を比較しましょう。
ステップ②:申込書を取り寄せ・提出
マイナンバーカード、年金手帳、勤務先の証明書類などが必要です。
申請後、2〜3か月で口座が開設されます。
ステップ③:掛金を設定
毎月5,000円〜上限まで1,000円単位で設定可能。
自動引き落としで積立投資が継続されます。
ステップ④:運用商品を選ぶ
投資信託・定期預金・保険などから選択。
長期運用に向くインデックス型投資信託が主流です。
6. メリット・デメリット
メリット
- 掛金が全額所得控除で節税効果が大きい
- 運用益が非課税
- 自分の年金を自分で作れる
デメリット
- 60歳まで原則引き出し不可
- 金融機関・商品により手数料が発生
- 転職・退職時は移換手続きが必要
7. 注意点(2025年時点の最新制度)
- 加入可能年齢は65歳未満(国民年金第1・2号・3号すべて対象)
- 受給開始は60歳〜75歳の間で選択可
- 企業型DCとの同時加入も条件付きで可能(企業がDC規約で許可している場合)
- 受け取り方法の選択自由度が拡大(一時金・年金・併用)
- 老後資金専用の制度であり、途中解約は原則不可
【根拠】
- 国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」
- 金融庁「個人型確定拠出年金の概要」
8. まとめ&今日からできる一歩
「iDeCoは“節税しながら老後資金をつくる制度”」
- 掛金が全額所得控除 → 毎年の節税につながる
- 運用益が非課税 → 長期運用で複利が最大化
- 受取時も控除あり → 税負担を最小限にできる
まずは金融機関を比較して、手数料が安く・インデックス型商品が多い口座を選びましょう。
関連記事:
【2025年最新版】NISAとiDeCoの違いを初心者向けに徹底解説!
9. FAQ
Q1. 60歳まで引き出せないのはなぜ?
→ 老後資金形成を目的とする制度のため、税制優遇の代わりに制限があります。
Q2. iDeCoと新NISAは併用できますか?
→ 可能です。NISA=中期資産形成、iDeCo=老後資金、と目的を分けて併用しましょう。
Q3. 転職や退職したらどうなる?
→ 「移換手続き」を行えば継続可能です。放置すると手数料負担が発生するため注意。